4.パソコンで作った文章や画像など、データ整理していますか? |
|
4−3 ●階層の話 |
私の場合1台のPCでDドライブに3G当てていましたがこの大きな分割でも、パソコンを使っていく内に、自作データや頂き物のデータはドンドン増えて行きました。(例えばホームページを作った事の有る方なら、HP作成をするだけで、アイコンやバナー、HTMLファイルなど即100個を越えるファイルが出来てしまいます。) 日常、ワープロでのあいさつ文章やら、年賀状の裏書き、エクセルの家計簿やら、年賀状ソフトのデータ等々、1年で個人の自作データだけでも、最低数10個はできると思います。 (ワープロのデータなんて、印刷してしまえば後はいらないって方は大きな勘違いです。一般個人の方は特に、新しい文章ってそれほど必要が無いので、1年間しっかりパソコンでデータ作成してしまえば、翌年からは以前のデータの一部変更のみで間に合ってしまう場合がほとんどです。また新規に作成するときに以前の文章の飾り付けや、割り振り等を参照する事もできます。ですから全くデータの無い状態から新規に文章作成するのと、データを参照するのとでは、作業時間に大きな違いが出ます。) さらにインターネットを利用していくとのデータは際だって増加していきます。マウスをクリックしてデーターをdownするだけでいいのですからデータは増えます。 |
これらのデータをDドライブの表面にベターーっと置いたらどうなるでしょう? 数十・数百のファイルが同じ場所に並び、どのファイルが必要なのか、どのファイルがどのアプリケーションの物なのか全く解らなくなります。 この状態を例えると、部屋の中に資料が散らかり、渦高く積もってる状態です。その様な中から1つのデータ(印刷された連絡文章など)を探し出すのは大変な作業になります。 会社や家でも紙の資料を保存するにも、先ず本棚が有って、各棚ごとに関係の資料を置きます。その上自作の文章やら、他所から来た手紙類は別のバインダに綴じて、決まった場所に入れますよね。 パソコンの中もこれと同様に考えてください。但しパソコンでは本棚・何段目・バインダでは無くすべてがフォルダと呼ばれます。 先ずドライブと言う大きな書庫が有ります。次にワープロ・エクセル・インターネット・ホームページ等、必要な複数のフォルダと言う本棚を作ります。次に各ソフトの利用状況に応じて、本棚の段に相当する(例えば仕事・家庭・学校など)フォルダを作成し、それでも1フォルダ内のファイル数が多いなら、(1月分とか99年度分)とかのバインダに相当するフォルダを作ります。 こうして作ったドライブを、Explorerで見ると、あたかもドライブ番号を幹とした樹木の(ツリー)形に見え、その枝ごとにフォルダを作成する事から、フォルダ階層の構造と言う名で呼ばれた訳です。 |
実際の階層例 |
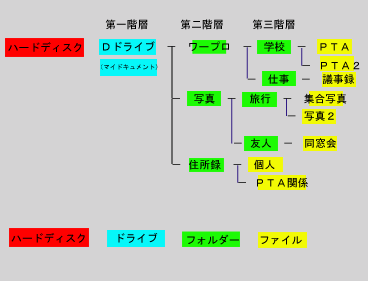 ハードディスクが一台のみの場合は、Dドライブのところが C:¥マイドキュメンのフォルダになります。 |
但し、むやみにフォルダを作る必要はありません。あくまで一画面のファイル名一覧表示で、ファイル一覧を表示しきれなく成ったときや、同じ名前のファイルを作成したくなったときに初めて、下層フォルダを作成し、そこへ種別してファイルをコピー保存すれば良いのです。(余りにも深い階層構造は、逆にファイルを呼び出したり保存したりするときに使いにくくなります。) MS-DOSの時代からパソコンを触っている方々は、フォルダーの事をディレクトリと呼んでいました。 つまり、Cドライブの様に大きな領域を総して、ディレクトリ、その下に作られるフォルダの事をサブ・ディレクトリと呼びます。従って階層構造の事はディレクトリ・ツリーと呼ぶわけです。 ディレクトリには他にもいろいろな制限事項や、決まり事が沢山有りますが、ここではややこしいので省きます。 |